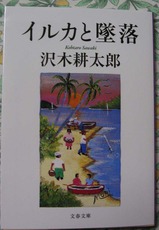「白旗の少女」 比嘉富子 著 講談社青い鳥文庫
「白旗の少女」 比嘉富子 著 講談社青い鳥文庫
・ ・・・・・・・
1945年4月、太平洋戦争末期の沖縄本島の南部。この日本最大の激戦地で、逃亡の途中、兄弟たちとはぐれたわずか7歳の少女が、たった一人で戦場をさまようことになった。しかし、偶然めぐりあった身体の不自由な老夫婦の献身で、白旗を持って1人でアメリカ軍に投降し、奇跡的に一命をとりとめた。この少女の戦場での体験をおった愛と感動の記録。(表紙の説明文より。小学校上級から。)
・ ・・・・・・・・・
表紙にも載せられている「白旗の少女」の写真は、1987年(昭和62年)「白旗の少女はわたしです」という見出しで新聞にとりあげられたので、私も眼にして驚いて記事を読んだことを覚えています。
今回、沖縄に旅行をした友人から勧められて読みましたが、本当に心から感動し胸が痛くなりました。この少女は私よりほんの3?4歳年上で、私が京都で戦争のことなど全く知らされず(私は2歳だからしかたない)のんびり生活している時に、沖縄ではこんな体験をされていたのです。
それと、少女を助けたおじいさんとおばあさんのもう言葉では言い表せない大きな愛!
・・・・・・・・・・・・・
「いいかね、外に出たら、その白旗がだれからでも良く見えるように高く上げるんだ。まっすぐにだ。いいかね、高く、まっすぐにだよ」と力強くいいました。これが、私が聞いたおじいさんの最後の言葉でした。
・ ・・・・・・・・・・・・
外に出るというのは、隠れていた洞窟から出るということで、白旗は、両手両足をもぎ取られたおじいさんが身につけていたふんどしで、目がみえなくなっているおばあさんが作ってくれたのです。
読みながら涙涙です。
小学生上級からとなっていますが、日本人みんな読まねばならない本です。
投稿カレンダー
2024年12月 日 月 火 水 木 金 土 « 2月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
最近の投稿
最近の投稿
- 蛍草 (2)
- ホーリーマザー・ポイズンドーター (2)
- 3/18 Breeze
- 3/18 Kiyoko Nagasaka
- 君たちはどう生きるか (8)
- 7/04 Breeze
月別アーカイブ
カテゴリー
メタ情報